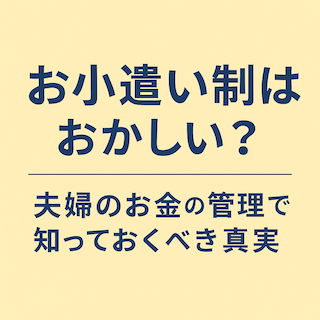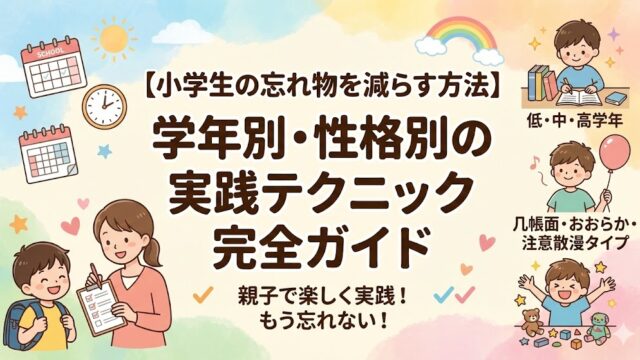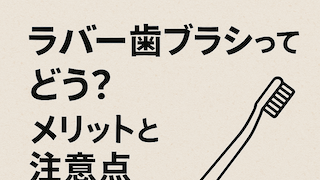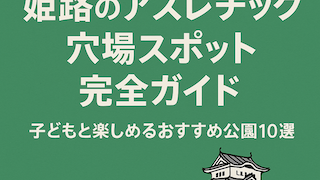12月生まれの七五三はいつする?最適な時期と準備のポイント
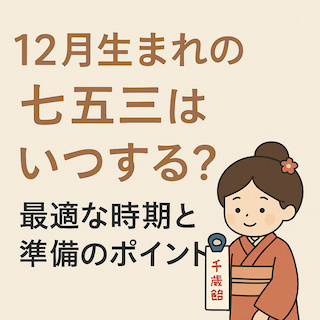
12月生まれのお子様の七五三について、いつお祝いするべきか悩んでいませんか?この記事では、12月生まれのお子様の七五三を行う最適な時期や、準備のポイントについて詳しく解説します。
目次
12月生まれの七五三はいつお祝いする?
七五三は、数え年で男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳にお祝いする日本の伝統行事です。12月生まれのお子様の場合、お祝いのタイミングについて迷われる方が多くいらっしゃいます。
数え年と満年齢の違い
| 年齢の数え方 | 説明 |
|---|---|
| 数え年 | 生まれた時点を1歳とし、毎年正月(1月1日)を迎えるごとに年齢を加える |
| 満年齢 | 生まれた時点を0歳とし、誕生日を迎えるごとに年齢を加える(現代の一般的な考え方) |
七五三は伝統的に「数え年」で行われてきました。数え年とは、生まれた年を1歳とし、1月1日を迎えるごとに年齢を加算する数え方です。一方、満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに年齢が増える現代的な数え方です。
12月生まれのお子様の場合、数え年と満年齢の差が大きくなるため、どちらで行うか検討が必要です。
12月生まれにおすすめの七五三時期
12月生まれのお子様には、以下の3つのパターンがあります。
| 基準 | 3歳の年齢(満年齢 or 数え年) | 備考 |
|---|---|---|
| 12月生まれ | 満年齢で3歳になる年 | 数え年では 4歳~5歳程度になる可能性 |
| 12月生まれ | 数え年で3歳になる年 | 満年齢では 1~2歳になる可能性が高い |
1. 数え年でお祝いする場合 数え年3歳の場合、実質満1歳代での七五三となります。12月生まれの場合、11月15日の七五三シーズンには、まだ満2歳になっていないお子様もいらっしゃいます。この時期は体が小さく、長時間の着物や参拝が負担になる可能性があるため、注意が必要です。
2. 満年齢でお祝いする場合 現代では満年齢で七五三を行うご家庭も増えています。12月生まれの場合、満3歳の七五三は翌年の11月頃に行うことになります。この方が子どもの体力や理解力が十分に発達しており、スムーズに進められることが多いです。
3. 早生まれと同様に考える方法 12月生まれは早生まれに近い時期のため、1年遅らせて満年齢でお祝いするケースも一般的です。お子様の成長度合いに合わせて柔軟に判断することが大切です。
12月生まれの七五三、どちらを選ぶべき?
数え年のメリット・デメリット
メリット
- 伝統的な方法で行える
- 兄弟姉妹がいる場合、一緒にお祝いしやすい
- 地域によっては数え年が一般的な場合がある
デメリット
- 子どもが小さく、着物や写真撮影が大変
- 長時間のお参りに耐えられない可能性
- イヤイヤ期と重なることが多い
満年齢のメリット・デメリット
メリット
- 子どもの体力や精神面が発達している
- 着物を着ることや写真撮影に協力的
- 思い出として記憶に残りやすい
- 着物のサイズ選びがしやすい
デメリット
- 伝統的な数え方からは外れる
- 兄弟姉妹との年齢差によっては一緒にできない
11月15日にこだわる必要はない
七五三の正式な日は11月15日ですが、現代では10月から12月にかけて、ご家族の都合に合わせてお祝いする方が増えています。特に12月生まれのお子様の場合、以下の時期がおすすめです。
おすすめの時期
10月中旬から11月上旬 混雑を避けられ、気候も比較的穏やかな時期です。神社も比較的空いており、ゆっくりとお参りができます。
11月中旬から下旬 七五三シーズンのピークですが、記念写真スタジオや神社は大変混雑します。早めの予約が必須です。
12月上旬 シーズンオフのため、神社も写真スタジオも比較的空いています。ただし、寒さ対策が必要です。
翌年に延期する 12月生まれで数え年が早すぎる場合、1年遅らせることで子どもの負担を軽減できます。
12月生まれの七五三準備のポイント
1. 早めの計画を立てる
12月生まれのお子様の場合、数え年か満年齢かを早めに決定することが重要です。家族で話し合い、お子様の成長度合いを見ながら判断しましょう。
2. 写真スタジオの予約
七五三シーズンの写真スタジオは数ヶ月前から予約で埋まります。特に人気のスタジオは、半年以上前からの予約が必要な場合もあります。前撮りを検討する場合は、さらに早めの計画が必要です。
3. 着物のレンタル・購入
着物のレンタルも早めの予約が安心です。12月生まれの場合、体格が小さめのことも多いため、サイズの確認は念入りに行いましょう。購入する場合も、成長を見越したサイズ選びが重要です。
4. 神社への確認
参拝する神社が決まったら、ご祈祷の予約方法や受付時間を確認しておきましょう。大きな神社では予約制のところも増えています。
5. 体調管理と当日のスケジュール
子どもの体力を考慮し、無理のないスケジュールを組みましょう。特に小さいお子様の場合、午前中の早い時間帯が機嫌よく過ごせることが多いです。
12月生まれならではの注意点
寒さ対策
11月から12月にかけての七五三は寒さが厳しくなる時期です。着物の下に防寒用のインナーを着せる、羽織やショールを用意する、足袋の下に靴下を履かせるなど、しっかりとした寒さ対策が必要です。
体調を崩しやすい時期
秋から冬にかけては風邪やインフルエンザが流行する時期です。七五三の前後は人混みを避ける、手洗いうがいを徹底するなど、体調管理に気をつけましょう。
イヤイヤ期への対応
2歳から3歳頃はイヤイヤ期の真っ最中です。着物を嫌がったり、写真撮影に協力してくれなかったりすることもあります。無理強いせず、お子様のペースに合わせることが大切です。
|具体的な事例ケース:12月生まれの場合、どうする?
ここでは「12月生まれ」の具体例を仮定して、どのような選択肢が考えられるか、年ごとに見てみます。
例 1:12月生まれで “数え年で3歳” を選ぶ
- この場合、満年齢ではかなり幼い年齢(1~2歳程度)で祝うことになる可能性が高く、着物を着せるのが難しいかもしれません。
- ただ記念として写真だけ残したい、もしくは母親方・祖父母方の意向を尊重したいという理由なら選択肢になるでしょう。
例 2:満年齢で3歳を待って祝う
- 一般的にはこちらの方が負担が少なく、衣装や撮影にも選択肢が多い。
- 他のお友達と同じ年齢で祝いたいという希望も叶えやすい。
例 3:満年齢で少し先(4歳・5歳時)に祝う
- 体力・発育・表情などを重視し、より良い写真・思い出を残したいと考えるなら、この調整も選択肢になり得ます。
- ただし、「七五三=3歳・5歳・7歳」の形式からやや外れるため、家族・祖父母との話し合いが必要。
年齢の数え方(数え年/満年齢)を兄弟と揃える必要は必ずしもなく、柔軟に組み合わせても構いません。
前撮りと当日参拝を分ける選択肢
最近では、写真撮影と神社参拝を別の日に行う「前撮り」が人気です。12月生まれのお子様には特におすすめの方法です。
前撮りのメリット
- 子どもの体力を分散できる
- 写真撮影にじっくり時間をかけられる
- シーズンオフに撮影すれば料金が安くなることも
- 天候に左右されにくい
- 衣装を2着楽しめるプランもある
前撮り時期の目安
6月から9月頃に前撮りを行い、11月に神社参拝をするパターンが一般的です。気候の良い時期に撮影できるため、お子様の負担も軽減されます。
まとめ:12月生まれの七五三は柔軟に考えよう
12月生まれのお子様の七五三は、数え年か満年齢か、そしていつ行うかについて、お子様の成長度合いやご家族の状況に合わせて柔軟に決めることが大切です。
伝統を大切にしながらも、最も重要なのはお子様の健やかな成長を祝い、家族で楽しい思い出を作ることです。無理のない計画を立て、お子様にとっても、ご家族にとっても素敵な七五三になるよう準備を進めましょう。
早めの計画と予約、そしてお子様の体調や機嫌を最優先に考えることで、12月生まれのお子様も素晴らしい七五三を迎えられます。ぜひこの記事を参考に、ご家族にとって最適な七五三のプランを立ててください。