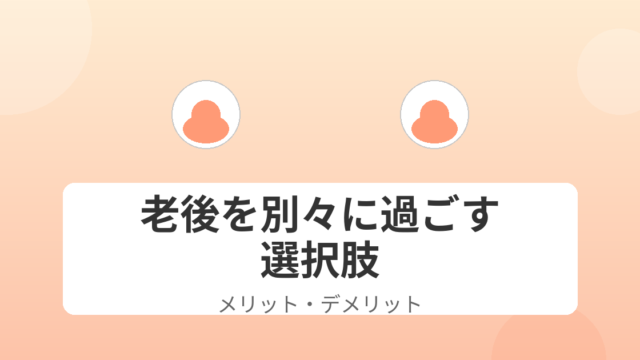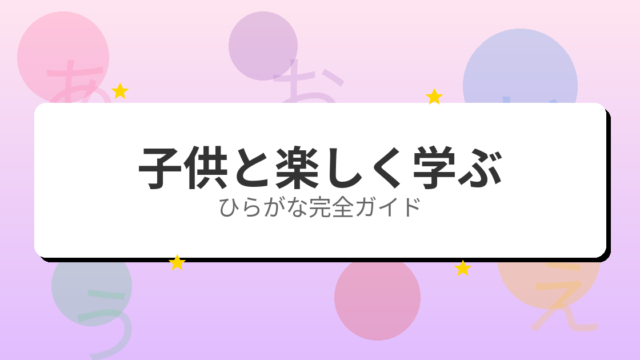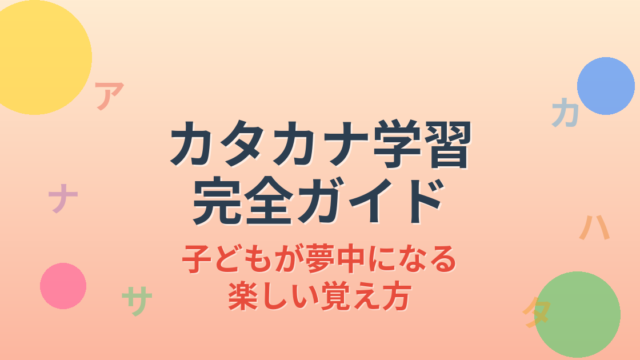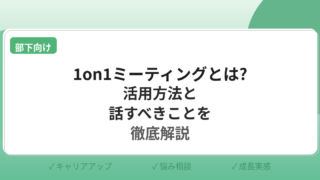【アドラー心理学の子育て】劇的にラクになる!叱らない・ほめない育児の秘密とは?勇気づけの実践法
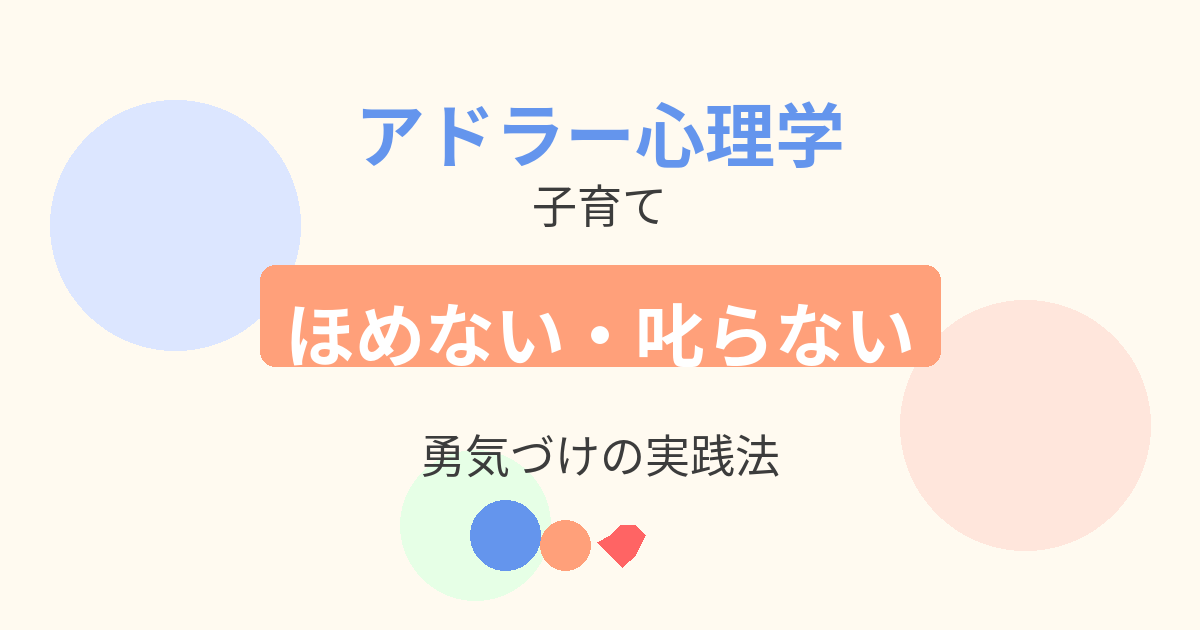
「毎日子どもを叱ってばかりで疲れた」「どうやってほめたらいいのかわからない」そんな悩みを抱えていませんか。
実は今、多くの子育て中の親が注目しているのがアドラー心理学を活用した子育て法です。この方法は従来の「ほめて育てる」「叱って正す」という考え方とは全く異なるアプローチを提案しています。
本記事では、アドラー心理学に基づく子育ての基本的な考え方から、日々の生活で実践できる具体的な方法まで、わかりやすく解説していきます。
目次
アドラー心理学とは?子育てにどう活かせるのか
アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーが創始した心理学です。フロイト、ユングと並ぶ心理学の三大巨頭の一人として知られています。
この心理学の最大の特徴は**「人間はみな平等である」**という考え方にあります。親と子どもも例外ではなく、対等な関係として捉えます。

子育てにおける3つの基本原則
アドラー心理学を子育てに応用する際、押さえておくべき3つの原則があります。
1. 親子は上下関係ではなく横の関係
親が子どもを上から評価したり、コントロールしたりするのではなく、一人の人間として尊重する関係性を築きます。
2. ほめない、叱らない
ほめることも叱ることも、実は親が子どもを操作しようとする行為だと考えます。代わりに「勇気づけ」という関わり方をします。
3. 課題の分離
親の課題と子どもの課題を明確に分けて考えます。子どもの人生は子ども自身のものであり、親が決めるものではありません。
なぜ「ほめる」子育てが問題なのか
多くの育児書では「子どもをほめて育てましょう」と推奨されています。しかし、アドラー心理学では「ほめる」ことにも問題があると指摘しています。
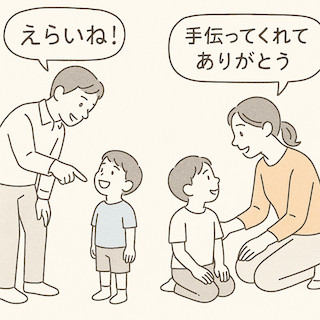
ほめることの隠れた問題点
ほめるという行為には「能力のある人が能力のない人を評価する」という上下関係が含まれています。つまり、親が子どもを上から見下ろして評価している状態なのです。
さらに、ほめられることに慣れた子どもは次のような状態になりがちです。
- ほめられることが目的になり、ほめられないと行動しなくなる
- 親の期待に応えることばかりを考え、自分で判断できなくなる
- ほめられる場面でしか行動できない、主体性のない子どもになる
叱ることの問題点
同様に、叱ることも親が上の立場から子どもをコントロールしようとする行為です。叱られて育った子どもは、自分で考えて行動する力が育ちにくくなります。
また、叱られないために行動するようになり、本当の意味での自立が妨げられてしまいます。
「勇気づけ」とは?アドラー式子育ての核心
アドラー心理学では、ほめる・叱るの代わりに**「勇気づけ」**という関わり方を推奨しています。
勇気づけの定義
勇気づけとは「自分や他者に、困難を克服する活力を与えること」です。
ここでいう「勇気」とは、自ら行動しようとする力、一歩前に踏み出そうとする気持ちのことを指します。
子どもが「自分には価値がある」と感じられるとき、勇気を持って新しいことに挑戦したり、失敗から立ち直ったりできるようになります。
勇気づけと褒めることの違い
| ほめる | 勇気づけ | |
|---|---|---|
| 関係性 | 上下関係 | 対等な関係 |
| 評価 | 親が評価する | 子ども自身が評価する |
| 目的 | 親の期待に応える | 子ども自身が成長する |
| 言葉 | 「すごいね」「えらいね」 | 「ありがとう」「嬉しかった」 |
今日から実践できる!勇気づけの声かけ5つ
では、具体的にどのような言葉をかければ良いのでしょうか。日常生活ですぐに使える勇気づけの声かけをご紹介します。
1. 「ありがとう」を伝える
子どもがお手伝いをしてくれたとき、「えらいね」ではなく「ありがとう、助かったよ」と感謝を伝えましょう。
これにより、子どもは「自分の行動が家族の役に立った」と実感でき、共同体への貢献を感じられます。

2. プロセスに注目する
結果だけでなく、努力や過程に目を向けます。「テストで100点取ってすごい」ではなく、「毎日コツコツ勉強していたね」と声をかけます。
3. 「私」を主語にして気持ちを伝える
「あなたは〇〇だ」という評価ではなく、「私は嬉しかった」「私は助かった」と自分の気持ちを伝えます。
4. 失敗を学びの機会にする
失敗したときこそ勇気づけのチャンスです。「次はどうしたらうまくいくと思う?」と子ども自身に考えさせ、失敗から学ぶ姿勢を育てます。
5. 子どもの存在そのものを認める
何かができたからではなく、「一緒にいてくれて嬉しい」「あなたがいてくれて助かる」と存在自体を認める言葉をかけましょう。
「課題の分離」で親も子もラクになる
アドラー心理学のもう一つの重要な概念が**「課題の分離」**です。
課題の分離とは
これは、その課題の結果を最終的に引き受けるのは誰かを考え、親の課題と子どもの課題を分けることです。
例えば、子どもが宿題をしない場合を考えてみましょう。
- 親の課題:子どもが心配だという気持ち
- 子どもの課題:宿題をするかしないか、その結果を受け止めること
宿題をしないことで困るのは子ども自身です。親が無理やりやらせても、子どもは自分で考える力が育ちません。
課題の分離の実践方法
- この課題は誰の課題か見極める
まず、その課題の結果を最終的に引き受けるのは誰かを考えます。
- 子どもの課題には介入しない
基本的に子どもの課題には口出しせず、見守ります。ただし、子どもが助けを求めてきたら、サポートします。
- 親の課題と混同しない
「子どもが心配」というのは親の気持ちであり、親の課題です。子どもの課題とは別に考えましょう。
アドラー式子育てで育つ子どもの特徴

アドラー心理学に基づいた子育てを実践すると、子どもにはどのような変化が現れるのでしょうか。
自立心が育つ
親に評価されるためではなく、自分で考え、自分で判断して行動できるようになります。
失敗を恐れなくなる
失敗しても責められないため、新しいことに挑戦する勇気が育ちます。
共同体感覚が育つ
自分の行動が周囲の役に立つという実感を通じて、社会の中で生きる力が育ちます。
自己肯定感が高まる
「ありのままの自分」が受け入れられているという感覚が、健全な自己肯定感を育てます。
まとめ:完璧を目指さず、今日から少しずつ実践を
アドラー心理学に基づく子育ては、「ほめない」「叱らない」代わりに「勇気づけ」を行い、親子が対等な関係を築く方法です。
重要なポイントは以下の3つです。
- 親子は横の関係であることを意識する
- 勇気づけの言葉がけを日常的に実践する
- 課題の分離を理解し、子どもの課題には介入しすぎない
完璧な親などいません。今日から「ありがとう」の一言から始めてみてはいかがでしょうか。
長い目で見れば、子どもは自分で考え、自分で行動できる自立した人間へと成長していくはずです。親も子も、共に成長していく。それがアドラー式子育ての本質なのです。